ニッポン長寿食紀行
vol.5「みそ汁」
個性豊かな菌が作り出した究極の長寿食、みそ汁
朝、幸せを感じるのが、食卓に並んだホカホカの白米とみそ汁。具はネギと豆腐、はたまた具だくさんの豚汁……。みそ汁はまさに、日本人のソウルフード。ひと頃は塩分過多になると敬遠された時期もありましたが、大豆を発酵させて作るみそは、タンパク質、炭水化物、ビタミン、ミネラルなど体に必要な栄養を含む長寿食。女性ホルモンと似た働きをするイソフラボンも豊富で、女性にこそ毎日飲んでほしい長寿食といえます。
というわけで今回は、おいしいみそを求めて、長野県須坂市でみそ・しょうゆの醸造業を営む〈塩屋醸造〉を訪れました。

〈塩屋醸造〉のある長野県のみそといえば「信州みそ」。「八丁みそ」や「仙台みそ」と並び、日本三大みその一つに数えられています。しかも、長野県のみその生産量は日本全体の約半分を占め、県民一人あたりの消費量も全国3位。そんな”みそ王国”長野県の中でも、〈塩屋醸造〉は有数の歴史を誇るみそ蔵。江戸時代末期の文化・文政年間(1804~1830年)から、みそを造ってきました。

「確かに歴史の古いみそ蔵ですが、それでも200年。和菓子屋さんや造り酒屋さんだと創業400年という老舗もありますから、比べものになりません。というのも、ひと昔前までみそは自分の家で造るものでした。だから商売にならなかったんです」と、案内をしてくれた11代目の上原太郎さん。
みそを家で造っていたなんて驚きです。でも、そんな簡単にできるものなの? というわけで早速みそ造りを見学です。

信州みその仕込みは、3月から4月が最盛期。そのため取材に訪れたこの日は、残念ながらすでに熟成中。そこで、熟成期間の異なる白みそ造りを見せてもらいます。工場の中は大豆を煮る蒸気でいっぱい。熱々に煮た大豆は細かくすりつぶして、かくはん機へ。大豆に塩と米麹をよく混ぜ、容器に移せば人の手のかかる作業は終わり。約半年熟成させればおいしい白みそが完成です。
え、これで終わり? 「信州みその場合は大豆を煮るのではなく蒸し、熟成期間が約1年と長くなるところが白みそとは違いますが、造り方は同じです。どうです、簡単でしょ?」
確かにこれなら家でも造れそう。おいしいみそを造るにはどうしたらいいのでしょう? 「味の決め手となるのは、一つにいい原料を使うこと。そしてもう一つ大切なのが、米麹です。米麹の出来が悪いと、絶対においしいみそにはなりません」
市販のみその多くは、原料に輸入大豆を使っていますが、〈塩屋醸造〉では大豆も米も全て長野県安曇野市の契約農家から仕入れています。米麹は、信州の名工に選ばれた職人さんが、丹精込めて作り上げたもの。そしてみそを熟成させる木樽とみそ蔵も、味を大きく左右するポイントです。
「長年、発酵や熟成に使ってきた木桶やみそ蔵には、乳酸菌をはじめとするさまざまな菌が棲みついています。この”蔵付きの菌”が味に深みを与えてくれるんです」
創業時に建てられた蔵は老朽化が進み維持も大変。それでもその味を次の代に伝えるために、修繕しながら大切に使い続けています。
薄暗いみそ蔵の中で目を凝らすと、棚に並ぶ不思議な塊を発見。「これはみそ玉といって、蒸した大豆をつぶして円柱状の塊にしたものです。2週間ほど蔵に入れておくと自然に菌がつくので、それを細かく砕き米麹と塩を混ぜて熟成させると『玉造りみそ』になります。米が貴重品だった江戸時代には、今のようにぜいたくに米麹を使えませんでした。それを補うための先人の知恵が、ずっと受け継がれてきたのです。手間はかかりますが、これも残していかなくてはならない文化だと思っています」

昔の味そのままの「玉造りみそ」で作ったみそ汁をいただきます。「あっ! おいしい」。一口飲むと大豆のうま味が口の中で広がります。そして蔵付きの菌が作り出した酸味。普段飲んでいる市販のみそとは風味が全く違います。これぞみそ汁! どこか懐かしさを感じる味わいは、みそ蔵の菌だけでなく、上原さん達の愛情が作り出しているのかもしれません。
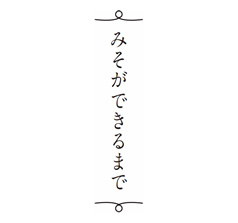




1. 煮た大豆を細かくつぶします。2. 米麹と塩を加えます。信州みそは大豆10 : 米麹10 が基本の米みそ。米麹の比率を多くすると甘め、少なくすると辛めのみそになります。3.大豆と米麹、塩をよく混合します。4.熟成期間の異なる白みその場合は、ポリ容器に移し、そのままみそ蔵で半年。信州みそは木樽に移し、みそ蔵で1年熟成させます。

